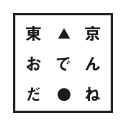今回は板かまぼこ(板付かまぼこ)のおでんの調理方法と日本各地での切り方について紹介したいと思う。

板かまぼこをおでんの具材に用いるのは中国・四国や九州地方が多く、東京ではあまり馴染みがない。しかし、一部のおでん種専門店では提供されている。切り方も複数あるので、調理法とともに紹介しよう。
おでんに入れても美味しい、板かまぼこ
板かまぼこは板付かまぼこともいわれ「かまぼこ」の代名詞的な存在だ。かまぼこは魚のすり身を原料とした練り物の総称で、製法により名称が異なる。

板かまぼこは製法上蒸し蒲鉾に属し、さつま揚げは揚げ蒲鉾、はんぺん(浮きはんぺん)やなると巻は茹で蒲鉾に属する。原料は一緒なので、どれもおでんの恰好の具材となる。板かまぼこはさつま揚げのように油を使っていないぶん、さっぱりとヘルシーに食べられる。

中国・四国や九州地方では板かまぼこをおでん種として用いることがある。紀文のオウンドメディア「オデンガク」によると「肉類で出汁をとる西日本では煮る時間が長く、火力も強いため、煮崩れしにくい板かまぼこを用いるのではないか」という考察をしている(参考:「オデンガク:中四国・九州はおでんに赤かまぼこ」)。

東京では板かまぼこのおでん種は馴染みが薄いが、江東区北砂の増英蒲鉾店ではできたておでんとして提供している。

蒲鉾の長辺に対して垂直に切るのは通常の切り方と同じだが、厚みは2cmほどある。紅白の蒲鉾を串に刺して鍋で煮ている。
しっかり味が染みていながら、煮崩れせず弾力を保っている。東京のおでん種専門店ではここでしか味わえないので、砂町銀座商店街に訪れた際はぜひ購入してみてほしい。
おでんの板かまぼこの切り方・調理方法
さて、ここからは板かまぼこのおでんを調理していこう。調理方法といってもいたって簡単で、切って鍋で煮るだけだ。

切り方は3種類ほどあり、地方によって異なる。それぞれ挑戦してみて好みの切り方を見つけよう。

用意する板かまぼこは高価なものでなくてもいい。量販店で販売している手頃なものでも味や品質は保証済みだ。今回は紀文の「鯛入り蒲鉾粋」と鈴廣の「小田原っ子」を用意した。

蒲鉾を板から外すときは包丁の背(峰)を使うといい。蒲鉾と板の間に包丁の背を入れるだけだが、包丁が入れにくい場合は蒲鉾の側面と包丁の側面を合わせ、蒲鉾を若干しならせると板の間に隙間ができる。

丁寧に外していけば、板に蒲鉾が残ることがない。綺麗にはがせたときの快感は格別のものなので、ぜひチャレンジしてほしい。

まずはスタンダードな切り方を紹介しよう。ほとんど説明不要だが、蒲鉾の長辺に対して垂直に切る方法だ。蒲鉾特有の扇の形が美しい。

包丁は薄刃のほうが切りやすいが、通常のものでかまわない。ノコギリのように押し引きせず、ひと息で切ると断面が美しく仕上がる。2cmほどの厚みにすると、煮てもほどよい食感を残すのでおすすめだ。筆者はいつもの癖で、板わさに最適な1.2cmで切ってしまった。

次に中国・四国や九州地方にみられる斜め切りに挑戦してみよう。圧倒的なボリュームで、ほかのおでん種に負けない存在感となる。

板かまぼこを丸ごと使い、中央を斜めに切る。長めの板かまぼこを使用する場合は半分に切ってから斜めに包丁を入れるといい。

最後は長崎おでんにみられる縦切りだ。細長いので串に刺すのに適した形状だ。

この形状はどこかで目にしたと思っていたが、葛飾区亀有を中心に営業する佃忠のなると巻と同じ切り方となる。関係性は不明だが、非常に興味深い。

切り方は蒲鉾の長辺と平行に中央で切る。長いものを使用する際は半分に切るなど長さを調節しよう。

好みの形に切ったら煮るだけだが、板かまぼこは竹串を刺して調理されることが多いので雰囲気重視でひと手間加えてもいいだろう。串が長い場合は先端を折って調節しよう。

あとは通常のおでんの調理法と同じように鍋で煮れば完成だ。板かまぼこはそのままでも食べられるので、さっと温める程度でいい。汁を染み込ませたい場合には10分程度弱火で煮て、冷ましてから冷蔵庫で落ち着かせるといいだろう。

温め直して器に盛り付ければ完成だ。定番のからしをつけても美味しいし、わさびでさっぱり味わってもいいだろう。崩れにくいので煮込んでも問題ないが、やりすぎるとうまみが汁に逃げてしまうのでほどほどにしよう。
おでんの板かまぼこは練り物のため、おでんとの相性は抜群だ。彩りも華やかにしてくれるので、すこし変わったおでん種を加えたいと思ったらぜひ試してほしい。